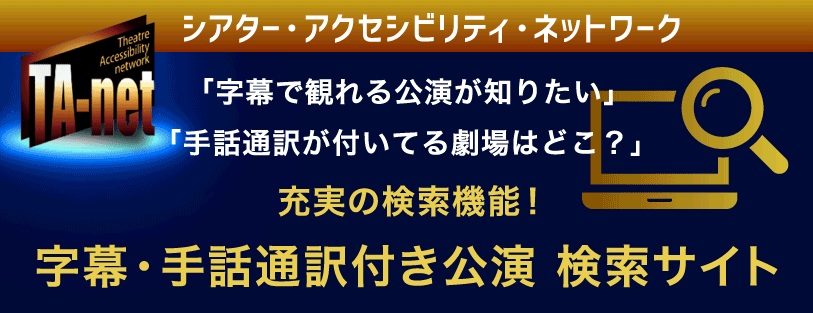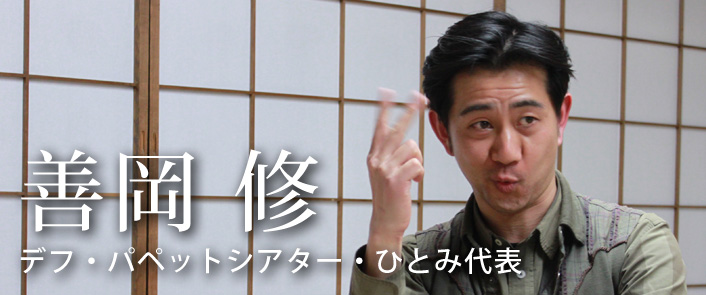
本日はお忙しい中、わざわざお越しいただき、ありがとうございます。「デフ・パペットシアター・ひとみ」代表の善岡修さんです。今日はいろいろと質問をしたり、インタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願い致します。
まずは、「デフ・パペットシアター・ひとみ」の活動内容を簡単に教えて頂けませんか?
「デフ・パペットシアター・ひとみ」と、ちょっと長い名前ですが、この劇団はろう者と聴者が一緒に作品を作る人形劇団です。本拠地は神奈川県川崎市にあります。北海道から沖縄まで日本全国で公演しています。現在ろうの団員は僕を含めて三名、聴者の団員三名、他に製作の担当者が三名と合わせて九名で活動しています。
素朴な質問ですが、どうして劇団の名前が「ひとみ」なのですか?

ろう者・聴者関係なく、「目」で見て楽しめ“視覚的表現”という意味で、「ひとみ」と名付けられました。
劇団を創立した方の名前が「ひとみ」さんなのだと思っていましたが、違うのですね。
「デフ・パペットシアター・ひとみ」が立ち上げられた経緯を教えて下さい。
劇団創立から今年で33年目と、長い歴史があります。1980年に立ち上げられました。デフパペットシアター・ひとみの母体が「ひとみ座」という人形劇団となっています。テレビで放映されていた「ひょっこりひょうたん島」という人形劇を知っていますか?その人形劇を担当していたのが「ひとみ座」です。(1948年創立63年)

ひょっこりひょうたん島

劇団を立ち上げる前の話ですが、アメリカから「デフ・シアター」というプロのろう者劇団が、来日しました。後に、劇団の産みの親となる宇野小四郎氏が観劇されました。アメリカ手話での芝居が中心に行われ、日本語やアメリカ手話の通訳がなかったにも関わらず、視覚的にも分かりやすく、ろう者だけで構成されているということに驚き、表現豊かなろう者と一緒に人形劇をやったら、魅力ある舞台になるのではないか、思い付き、今の劇団が生まれました。
その頃、同じタイミングで立ち上がったグループがもう一つあります。
日本ろう者劇団です。自分たちとは別のグループですが、目指しているものは一緒ですね。33年前と言ったら、沼倉くん(インタビュアー)が生まれる前ですし、僕もまだまだ小さい時です。五才か六才ぐらいですね。
長い歴史があるのですね。
善岡さんは最初から演劇に興味があったのですか?
実を言うと、演劇には全く興味はなかったのです。
この世界に入ろうと決めたのは、いつからですか?
10年前、2002年からです。27才でした。
今の僕と同じ年ですね。入ろうと決めたきっかけは何だったのですか?
この話をすると、とても長くなりますが大丈夫ですか?(笑)
僕は人形劇や舞台に立ってお芝居をすること、表現することは得意ではないし、あまり興味もありませんでした。僕は北海道出身で、ろう学校を卒業し、関東の職業訓練学校に通ったあと、神奈川で一人暮らしをしながら仕事を始めました。そんなときに、たまたまFAXで「ろう者のための映画を作るけどどう?」というお誘いがありました。

当時は若かったので、ノリで「やろう、やろう」と二つ返事で決めました。映画の内容はサスペンスでした。当時の手話を扱ったドラマといえば、涙を誘うような内容が主流で、ろう者が殺される、その殺した犯人もろう者というろう者が前面に出てきたサスペンス映画は、とても珍しいものでした。

ろう者のサスペンスドラマ
それが上映されると反響を呼び、日本各地でも上映会を行いました。その時に、お客様の生の声や意見を聞く機会が多くありました。ほとんどの方から「良かったよ」と言われる中で、ある人からは「君は手話が下手だね」と言われて、大変ショックを受けました。
改めて、自分が出ている映画を観ると、今の自分の手話と、昔の若い時の手話は確かに違いました。昔の自分は日本語に合わせた手話で指文字も多用したので、ろう者の手話は、日本手話でないとダメなのかと、思い込んでいました。そういう意味で下手だと言われたのだと思います。
しかしその時、監督からは、「ろう者といってもいろんな人がいる。手話の上手い人もいれば手話の出来ない人もいる。地域によって様々な手話がある。それでいて会話が成立している。それが出来れば、日本語対応手話でも良いんだよ」と言われて、自信を取り戻し、次の映画作りの機会があったらもっと頑張ろうと思いました。
次の映画にも出演して、良い反響を頂きました。「デフ・パペットシアター・ひとみ」の当時の代表の庄崎隆志さんが映画を観てくれて、僕に「舞台に出てみないか」とおっしゃっていただきました。舞台で演技する経験はこれまでありませんでしたが、終わってみれば、たくさんのお客様から大きな拍手をもらって、とても嬉しかったです。すっかり演劇の世界に目覚めてしまいました。しかし残念な事に、僕は会社員のままでしたので、また月曜日から普通に仕事をしなければなりません。昨日まで舞台に立っていたという余韻が残ったまま会社へ出勤するのは辛かったです。「もう一度観たい!」と言っていただける方がたくさんいましたし。今度は、庄崎さんから「デフ・パペットシアター・ひとみ」に入団しないかと声をかけて頂いたときは、もう既にやりたい気持ちが強く、すぐ入団を決めました。
迷いはなかったのですか?
ありませんでした。でも冷静に考えてみれば、デフパペットをまだ観たことがなかったので、劇団に入る前に観てみました。
頭のなかのイメージがどんどん膨らんでいき、大変刺激的でした。僕の友人で、手話を知らない聴者も一緒に観ていたのですが、彼も内容を理解できたようです。ろう者も聴者も同時に理解できて、共に感動したり笑ったりできるということはとてもすごい、とのことでした。僕も大変気に入り、自信を深めることができ、入団を決めたというわけです。

僕は今まで、パペットシアターを観たことがないので、イメージしづらいのですが、手話とパペットのつながりはあるのですか?
通常のパペットとデフ・パペットの違いが知りたいです。
違いはもちろんありますよ。一般の人形劇では、人形遣いが隠れる衝立から(※ケコミともいう)人形を上に掲げながら、声を出して喋っています。 聴者のお客様はそのセリフを聞いて、楽しみます。逆にろう者から見た場合、止まったままの人形を見ても、なぜ人形が止まっているのかと内容を理解しにくいです。
声を使っての台詞にこだわりすぎずに、もっと人形の動きをはっきり見せれば、聞こえる聞こえないに関わらず、(人形の)動きに意味を見出せるし、セリフは体や顔だけで十分表現できる、という考えをもとに、(デフ・パペットが)できました。
人形と手話だけではなく、セリフについても様々な(演出)方法があります。
例えば、漫画の吹き出しのようなプラカード。怒った時は(吹き出しの形が)とがってみえる、というような方法です。実際に人形のとなりに吹き出し(のボードのようなもの)を見せます。つまり人形を持った人形遣いが実際に声を出してしゃべるだけではなく、吹き出し担当の人が人形の動きに合わせて吹き出しを見せます。内容が悲しいときは、吹き出しもゆらゆらと下に落ちるように表現します。
人形の隣に手話によるナレーターもいて、手話で語る方法もあります。また、人形が手話を使うこともあります。二人羽織のように、(人形遣いの)後ろの人が手話を使うのです。他にも、プロジェクターで幕や役者の身体に文字を投映する方法もあります。
このようにセリフを様々な方法で工夫しました。ろうのお客様も楽しませるためにはどうすればいいか、聴者やろう者(の団員)同士で話し合っては、アイデアがどんどん生まれています。
聴者とろう者が話し合っていると、何かしらの壁ができてしまうと思うのですが、その際の苦労などはありましたか?
うーん、ろう者同士でも意見の違いなどはありますからね。別に聴者だからといって壁を感じることはないと思います。人の考え方はまちまちなので、壁ができてしまうのは当たり前です。それをどうやって(解決するか)。・・・考え方が違うのも、それらをうまくすり合わせないといけないと思います。点在した点と点がより中心に集まるように、全員が共通した目的を持つことが大事です。
つまり、みんなの目的が同じであれば…
同じ目的に向かっていく途中であれば、壁ができても構わないと思います。
例えば、僕が、ろう者を楽しませたい!という立場で考えていて、聴者から「聴者のお客様も楽しませたいけど、そのためにはどうしたら良いかな?」と言われた時に、「知らんわ!関係ないわ」と答えたらおかしいですよね。どちらも「お客様を楽しませたい」という目的がありますから、あまり「ろう!ろう!」とこだわりすぎても、おかしいですよね。お客様はろう者だけではないので、誰もが楽しめる内容にするにはどうしたら良いのか、十分に話し合う必要があると思います。

なるほど。
お客様のほとんどはろう者ですか?年配者や若者、劇団関係者などどんな観客がいらっしゃいますか?
ろう者も聴者もいらっしゃいます。どちらかというと聴者が多いですね。そもそも障害者の割合は、多くはないですよね。手話を使う聴者や、手話が分からない聴者もいます。子連れの方も年配者の方もいらっしゃいます。外国の方も、セリフにこだわらない内容のため、観に来ていただいています。
盲聾者もいらっしゃったことがあります。盲聾者はどのようにして観るのかといいますと、開演前に、優先的に入場してもらい、人形を実際に触っていただくんです。
人形の輪郭を触れながら、「あ、これはたくましいから男の人なんだね」「もう1つのは、胸があるから女の人なんだね」など劇中で登場する人形の特徴を覚えてもらい、観劇中は「あ、今のはさっきの男と女が喧嘩してるのか」などイメージをわかせます。終演後も、会場に残っていただき、人形の質感や大きさなどを改めて感じていただき、イメージの答え合わせをしています。
人形劇は良いですよ!こうやって実際に人形の顔に触ったりすることができるから、盲聾者の方にも楽しんでもらっています。演劇の場合だと、役者さんの顔をペタペタと触るわけにはいかないですからね(笑)本当に様々な方々に観ていただいています。

それに、(デフ・パペットシアターが)コミュニティスペースにもなっているんです。ろう者も聴者も楽しめる劇だったら、どなたでも気軽に観に行けますよね。
観劇に来られた方が隣の人に手話で話しかけてみたら、意外と近所に住んでいたりと、身近に感じて、交流のきっかけにもなるんです。誰もが楽しめる劇であれば、観にいくことで手話に興味を抱いてくれる一般の方や、ろう者の出会いもあったりします。そういう出会いの場にもなっていますから、人と人とのつながりも生まれます。とても良い場所だと思います。
劇だけではなく、コミュニティという場で人と人がつながる機会を提供しているんですね。良いお話しですね。
劇を観るだけでなく、様々な出会いも得られるのは素晴らしいことだと思います。
福祉というのはろう者だけでなく、いろんな障害を持つ人々も平等に娯楽を楽しむ文化が出来てこそ福祉だと思うんです。
聴者からすると、初めて知ることも多くあります。開演前の「上演中の食事は禁止」などの場内アナウンスを、聴者は何気なく聞いていますが、ろう者はアナウンスが分からず、何事かと不安がる様子を見て、聴者は初めて気がつくんですね。ろう者のお客様が来ることで、初めて気付くことが多いんです。
これは、良い機会なんです。こういうことがあることで、またろう者のお客様がお見えになられたときに、活かせば良いのです。手話通訳をつけるともっと良いですよね。また、車いすの人が観にいこうと思ったら、会場には階段があったりとか・・・。そんなときは周りの人に助けてもらって上の階に上がったりしますよね。今度上演するときはスロープにして、という不満の声もあります。このように不満が生じてしまっても、次の機会でプラスになるように活かせば良いんです。
つまり、ろう者が来るか、聴者が来るか、盲の方や車椅子の方などどのような方々が来るか分からない中でやっていて、初めて気付くこともあるということですね。
当日は、どんなお客様が来るかは分かりません。
上演の時は、ろう者や手話というアピールはしていないのですか?
デフ・パペットの上演チラシには「ろう者と聴者が共に作り上げた劇団です」という説明文はありますが、「ろう者」とは強調していません。
誰もが楽しめることを目的にしていますからね。
ただ、宣伝する時は気をつけないと誤解されることがあります。「私、手話分からないからろう者の出ている舞台はちょっとね・・・」という方もいます。でも、地域の方の理解や、デフ・パペットを応援いただいている方々が、「(手話が分からなくても)大丈夫だよ」など(誤解を解くように)色々とPRを頑張っていただいたおかげで、聴者の方々にも、楽しめる内容で、「とても良かった!」と言っていただけています。そのようにして次々とつながるんです。
防災人形劇「稲むらの火」は三年間で107回公演してきたということですが、それはろう学校で公演されていたのですか?

稲むらの火
はい、ろう学校だけです。
同じろう学校で何度か公演したということでしょうか。
いえ、公演したのは1校につき1公演だけです。一般の学校での避難訓練は地域の消防署を招き、その話を聞きながら防災意識を高めたりします。
例えば、地震が起きた時はどうしたら良い?という説明のとき、「ラジオで情報をつかんでから、行動してください」とろう者に向けて説明したら、それはおかしいですよね。火事が起きたら119の電話が必要だとろう者に向けて言っても、通用しないわけです。
そういう意味で、ろう者に合わせた内容に作り上げていき、劇を通して防災の人形劇をやるんです。
少子化が進んでいる学校もあり、私たちを呼びたくても呼べないという学校もありますが、交通費や宿泊費など必要な資金は助成金のおかげで、学校側はスケジュールを調整するだけで公演ができるように体制が整っています。
実際に舞台を観ていただいて、ただ楽しいだけで終わるのではなく防災に対する意識を高めるために、全国あちこちへ行って公演を行っています。
デフパペットを観た子供たちの反応はいかがですか?
楽しんでいる様子がみられました。子供たちの豊かな想像力で、防災意識を高めようというのが感じられたので良かったと思います。
でも、今の若い世代は僕らの世代と比べ、想像力が落ちているように感じています。やはり、インターネットやテレビゲームの影響でしょうか。欲しい情報がすぐ手に入る時代、これではやはり想像力は落ちてしまいます。昔は、そういうツールがなかったので、話を聞いただけで、自分の想像に頼る部分もあったのですが、今だとちょっとネットで調べれればわかりますからね。

避難訓練で、防災について小学生に説明する時、ラジオで状況を確認したり電話で連絡をとったり、という話があると思うのですが、ろう者に対してはどのように説明するのでしょうか?
僕は150年前に実際起きた津波から村人の命を救ったという「稲むらの火」の人形劇を見せた後に、おまけタイムの時間を設けています。
ろうの子ども達と災害が起こった場合困る事は、なんだろう?と舞台上から子ども達に聞きます。例えば、「洪水に遭った時はどうしたらいい?」という聞いた時に、子供たちに考えさせるというスタンスを取っています。
そして、実際災害が起きた場合、聴者たちとどうやってコミュニケーションをとっていくのかについて、話し合ってもらいます。例えば筆談です。相手が手話が出来なくても、筆談だったら通じます。そのことを気づいてもらいます。
公演が終わったあとに東日本大震災があったと思うのですが、成果は現れたのでしょうか?
実際、校舎は倒壊したにも関わらず、全員無事だったと話を伺っています。
それは良かったですね。
この防災についての劇「稲むらの火」は、今後も継続していくのでしょうか?
本来なら、全国107のろう学校での公演を終えたら、一区切りとして終わる予定でしたが、ぜひ聴者の学校でもやっていただきたい、というオファーがありました。こないだも横浜市内にある小学校へ公演しに伺ったのですが、その小学校のそばには海があるんですね。
町内会や家族たちが資金を集めていただいたおかげで、公演が実現しました。先ほど話したのと同じように、聴覚障害者についての話をしたのですが、手話を初めて観る小学生が多く、とても興味を持っていただけました。
災害が起きると、聴覚障害者の存在を忘れしまいがちなので、どう対応したらいいか気付かせるのに良い機会だと思います。

公演の内容は、聴者向けや、ろう者向けと、観客者を限定しないとおっしゃっていましたが、観る側の(両者の)反応はやはり違うものになってきますか?
そうですね、楽しいことや恐ろしいことの感情は、ろう者も聴者も大差ないのですが、聴者の方は災害の時に情報が行き渡らないろう者の存在に「今まで気付かなかった」「タメになった」と言ってくれました。
今後の展開について、たとえば海外進出などは考えていますか?
海外での公演の話もありました。だいぶ前にはインドネシアからのオファーがありました。スマトラ沖地震があり、津波の被害を受けた地域ですよね。
「デフ・パペットシアター・ひとみ」の今後のビジョン、目標を聞かせてください。
ろう者と聴者と協同しておもしろい舞台を創ることはもちろんですが、若い世代を巻き込んで、第二世代を作っていきたいです。
また、インターネットの動画で劇を観るんじゃなくて、実際に足を運んで生の舞台を見ていただくには、どうしたらいいか?それを考えていきたいです。
インターネットでは、立体で観ることができませんが、デフ・パペットシアター・ひとみの舞台だったら3Dメガネをかけなくても迫力がありますからね(笑)

こないだ、「五輪書のぼうけん」という劇を観にいったのですが、やはり生の舞台ならではの雰囲気、迫力、匂い、観客の反応などが相まって、役者の真剣な気持ちが伝わってきました。そういうアナログな部分はいくらインターネットが発達しても、カバー出来ない部分だと思うのです。内容を知るだけでしたら、インターネットで十分ですが、気持ちや感情を感じたいならやはり生の舞台を観ることですね。
やっぱり、僕たちはお客様との真剣勝負で取り組んでいますからね。例えばですよ、サッカーのスタジアムを想像してみてください。サポーターがたくさんいるのと、少ないのとで、選手の気持ちの入り方が違ってきますよね?
スタジアムいっぱいにお客様がいたら、この試合は重要な試合だ、負けられない、と思ってしまいます。お客様も同様に燃えて、選手も燃える。それは劇も同じなんです。たくさんのお客様がいると劇に対する気持ちの入り方も変わってきます。
これまで劇を長くやっていらっしゃいますが、やはり緊張は慣れないものですか?
毎回毎回緊張しています(笑)
実は、劇よりもこのインタビューの方が緊張していますよ(笑)だって、このインタビューは台本がないでしょ。劇の場合は、台本があって前もって何回も繰り返し稽古があるので、ある程度自信を持てるんですが、このインタビューはそういうのが一切ないので、不安になっています。この記事は、何億人か見ていますよね?

いやぁ、億までは行きませんが、数十万人の方に見ていただいてますね(笑)
最後に、善岡さん個人の目標をお聞かせください。実はそこが個人的に一番聞きたいことです。
(考え込む)

やっぱり、僕個人と劇は切っても切り離せないです。劇で食べていけるようにしていきたいです。劇で食べていく事はかなり大変なことです。世間の目から見ると、安定した生活を求めるのが普通だと思いますし、劇をやっているとやはり、収入にばらつきがあります。実際、劇を始めるときは色んな方に反対されましたし、頭おかしいんじゃないの?と心配されました。でも、僕は劇を始めて十年経った今、そういう馬鹿さも大事だと思えるようになりました。だから、これからもこの馬鹿さを大切にして、劇を続けていくのが目標です。それから、まだ見た事がない世界を色々と見るのも目標のひとつです。
ありがとうございます。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。
善岡さんから動画メッセージをいただきました。(03分08秒)
「デフ・パペットシアター・ひとみ」のウェブサイトはこちらから!

森と夜と世界の果てへの旅
2014年3月28日〜30日 神奈川芸術劇場(KAAT)にて、公演決定!

インタビュアー: しかく 沼倉昌明